
柏原、荻は三原(柏原・恵良原・葎原)と言って、江戸時代から明治にかけて、村内を流れる大谷川、岩戸川、滝水川の川沿いに僅かに田んぼがあるだけで、土地は畑と山林原野で、村人は火山灰土のやせた土地に陸稲、とうもろこし、大豆、菜種等を作って生活していたから暮らしはとても貧しかった。
田んぼを造るため水を引くにも、田んぼより川が低く、人や家畜の飲み水さえ、谷底から牛馬の背か、人の肩によって担ぎあげるか、深い井戸を掘るほか方法がなかったのです。
幾馬の父小八郎は、そな村人の様子を見かねて、荻町に水を引く「井路」を建設することを決意しました。
井路を建設するには莫大な費用がかかります。まず、小八郎は政府に援助を求めに行きました。
ところが、「政府は出来たばかりで財政がなく援助が出来ない」と断られてしまったのです。
明治12年。小八郎は、同じく大野川上流から水を引く計画を持つ高城村の工藤祐鎮と出会います。
明治23年(1890)知事に普通水利組合設立を願い、翌年許可を受け、着工のはずだったがなかなか請負者が決まらず、
決まっても工事費の工面が出来ず、着工出来ませんでした。
工事は中止となり、明治45年(1912)、小八郎は井路の完成を見る事なくこの世を去りました。
昔の柏原、荻

水はなく生育は不安定であった。



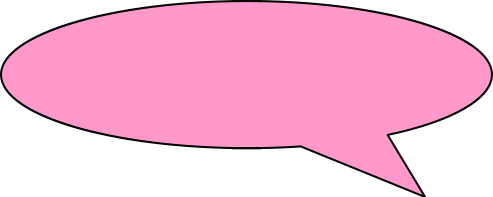
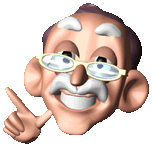
※ クリックすると大きな画像を見ることが出来ます。